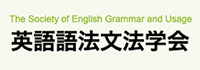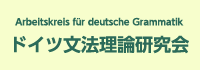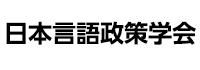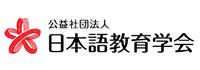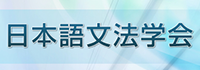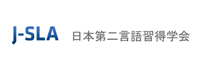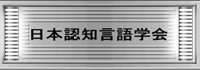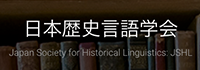お知らせ
NEWS
主催:日本言語政策学会
共催:日本フランス語教育学会
グローバル化の深化する現代日本において、物理的心理的な国境の壁はますます低くなり、それに伴い言語教育の目的や教師の役割は揺らいでいます。言語教育は知識の伝達にとどまることなく、コミュニケーションを通じたアイデンティティーの形成、異文化との関わりなど、教育目的の多元化を迫られています。
日本社会は人口減少に直面し、外国人人口の増加する中で日本語によるコミュニケーションに向けた言語教育の位置づけ、急速に発展するAIに直面する英語教育、さらには大学教育改革の中で存亡の危機に直面している英語以外の外国語教育など、言語により抱える課題は異なるにせよ、従来の言語教育に大きな変化が迫られていることに変わりはありません。
このような時代や社会認識のもと、このシンポジウムでは、教授法や制度、教員養成、学会の存続などとの関連から言語教育の過去、現在、そしてこれからを展望しながら、異なる言語教育間の相互理解を進め、今後の言語教育に新たな活路を開きたいと思います。
日程:2025年3月3日(月)
会場:中央大学茗荷谷キャンパス
参加を希望される方は下記のURLからお申し込みください(入場無料)。
【申込受付フォーム】https://forms.gle/UsKjzyjzFY9DChqs7
基調講演13 :00~13 :30
講演者 江利川春雄先生(和歌山大学・英語)
「日本の外国語教育政策史を問い直す」
幕末から現在までの日本の外国語教育政策史を概観し、その特徴・問題・展望を探る。考察の重点は、外国語教育政策の経済・政治・軍事への依存、脱亜入欧策と西洋言語偏重、英学本位制と英語帝国主義、立身出世と受験英語、教養軽視の実利主義、英文科の凋落とコミュニケーション重視の破綻、歴史無視・検証放棄の政策的迷走、新自由主義によるエリート育成と格差の構造化など。歴史から学び、現状を問い、未来を展望したい。
シンポジウム1 13 :45~15 :45
日本語(神吉宇一先生、武蔵野大学)
「日本語教育を通した共生社会の実現と日本語教育者の専門性」
日本国内の日本語教育の実施に関する法律・政策の整備が進んでいる。特にCEFRを参考にした「日本語教育の参照枠」は日本語教育の目的・内容のあり方を示したものとして注目されている。しかしこのことは、ミクロな学習活動において、素朴なcan do主義とでもいうような事態を引き起こしつつある。また、今般、都道府県や市区町村が日本語教育事業を実施しようとしているが、その受け手としての専門機関がなく、日本語教育が実施できない現状がある。地域社会においてことばの教育の社会的価値や意味をどのように見出していくかというメゾレベルの専門性を持った専門家の育成が課題として顕在化している。
中国語(村上公一先生、早稲田大学)
「中国語教育をめぐる諸問題」
科学技術の進歩とそれにともなうグローバル化の進展により外国語教育を取り巻く環境が大きく変わりつつあり、中国語教育も他の言語と同様にその荒波にもまれている。それに加え、中国が日本にとって地理的・歴史的に近い関係にあることにより生じている問題がある。例えば、日本における中国語教育は日中間の政治的な関係に大きく左右されてきた。学習者数もそれをトレースするように増減を繰り返している。また近年では母語・継承語教育も中国語教育における重要なテーマとなっている。
朝鮮語(中川正臣先生、城西国際大学)
「日本における韓国語教育の課題:多文化共生社会の実現に向けて」
20世紀後半から21世紀にかけて韓国語学習者は急増した。これに対応すべく韓国語教育関連の学会や研究会の活動が活発化し、教師教育も進められてきた。また、従来は在日コリアンを主な対象としていた継承語教育は、ひろく日韓につながる子どもたちに対する教育へと変化している。近年では日中韓三言語教育の連携の試みも見られ、多言語教育のつながりも模索され始めている。射程を広げる韓国語教育にいかなる課題があるのか。今、求められる韓国語教育について考えたい。
ロシア語(横井幸子先生、大阪大学)
「日本における外国語としてのロシア語教育の現状:パンデミックとウクライナ侵攻を経て」
パンデミックとウクライナ侵攻を経て、日本のロシア語教育を取り巻く環境は大きく変化した。ロシアへの渡航ができない中、ロシア語学習者の海外研修先は旧ソ連、東欧諸国といったロシア語が歴史的に話されてきた多言語社会が中心になっており、ロシア語教育は、ロシア語・ロシア文化だけに限定しない多言語・多文化教育を視野に入れる必要が生じている。日本ロシア語教育学会では、このような特殊な事情を踏まえて多言語性を重視したロシア語教育の新たな方向性を検討し、教員養成や教育現場での実践に向けた具体的な高大接続の可能性を探っている。
司会:村岡英裕(千葉大学、日本言語政策学会)
シンポジウム2 16 :00~18 :00
英語(飯野公一先生、早稲田大学)
「言語政策としての大学グローバル化推進事業 ― 「英語で学ぶ」EMIと英語の多様性について」
大学グローバル化推進事業(スーパーグローバル大学創成支援事業、EMI<English-Medium Instruction>プログラムの増設、留学生受入れ・送出しの促進等)の導入から10年以上が経過し、大学における英語教育のあり方も大きく変化しつつある。本シンポジウムでは、専門科目を「英語で学ぶ」EMI学部、大学院プログラムの実態と課題を取上げ、多様な参加者による多様な英語使用、英語以外の言語の役割、教員採用時の資格要件、関連学会の動向等について理解を深める機会としたい。
ドイツ語(境一三先生、慶應義塾大学・獨協大学)
「日本のドイツ語教育と教員養成・研修の実情」
ドイツ語は、履修者減に歯止めがかからない。1997/98年の調査では、大学の履修者数は合計34万5千と推定されたが、2012年の調査では22万人程度と激減している。近年は大規模調査が行われていない。教育目的は、かつては専門教育で文献読解に必要な力をつけることとされていたが、その目的は今日ではほぼ存在しない。高校教員養成のための授業は存続しているが、履修者数は少ない。研修は、ゲーテの他、日本独文学会のドイツ語教員養成・研修講座がある。独文学会は会員数が減少の一途を辿り、地方支部の存続が危ぶまれる状況である。
スペイン語(大森洋子先生、明治学院大学)
「スペイン語教育の現状、実践と今後の課題」
スペイン語教育に関しては、スペイン語を勉強したのち教育そのものに興味を抱き、研究を続ける人が多くなった印象である。教育の現状としては、1、2年での学習に集中されるため、コミュニケーションができるようになることを目的としていると言える。スペイン語教師としての教職への就職が難しい現状では、英語以外の外国語の教職課程を履修する学生が減少していることは否めない。学会、研究会レベルでは教育をテーマにした研究発表も多くなり、関係する学会の協力体制を強化することで、更なる教育の充実が図られると思われる。
中等教育(山崎吉朗先生、日本外国語教育推進機構)
「中等教育における英語以外の外国語教育の現状と展望」
学習指導要領では、英語以外の外国語を学習することが認められている。しかし、高等学校での英語以外の外国語設置は、2021年の調査では約12.4%、履修者は約1.3%に過ぎない。グローバル化、国際化が声高に叫ばれている中、中等教育の現場では、英語以外の外国語を学習する機会が奪われている。日本の地位が低下していく中、果たして、これでよいのだろうか?日本外国語教育推進機構JACTFLは、2024年9月30日に、文部科学大臣、初等中等教育長、外国語教育推進室長に対し、次期学習指導要領「外国語」に、英語を中心とした複数の外国語学習を奨励する方針を記載することを提言した。
フランス語(小松祐子先生・お茶の水女子大学、日本フランス語教育学会)
「フランス語教育の現状と課題~日本フランス語教育学会の取り組みを中心に~」
日本におけるフランス語教育は大学設置基準大綱化後も一定の需要を保ってきたが、今後は加速する少子化やAI技術の発展・普及による影響が危惧される。日本フランス語教育学会は1970年の創設以来、研究と教育実践の両面にわたり活動を続けてきた。教員研修や教授法研究会を開催し、実践的な知識・技術の共有に努めている。さまざまな専門分野をもちながらフランス語の授業を担当する多くの大学教員の関心をいかに高めるかが課題である。
司会:村田和代(龍谷大学、日本言語政策学会)
全体討論18 :00~18 :20